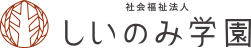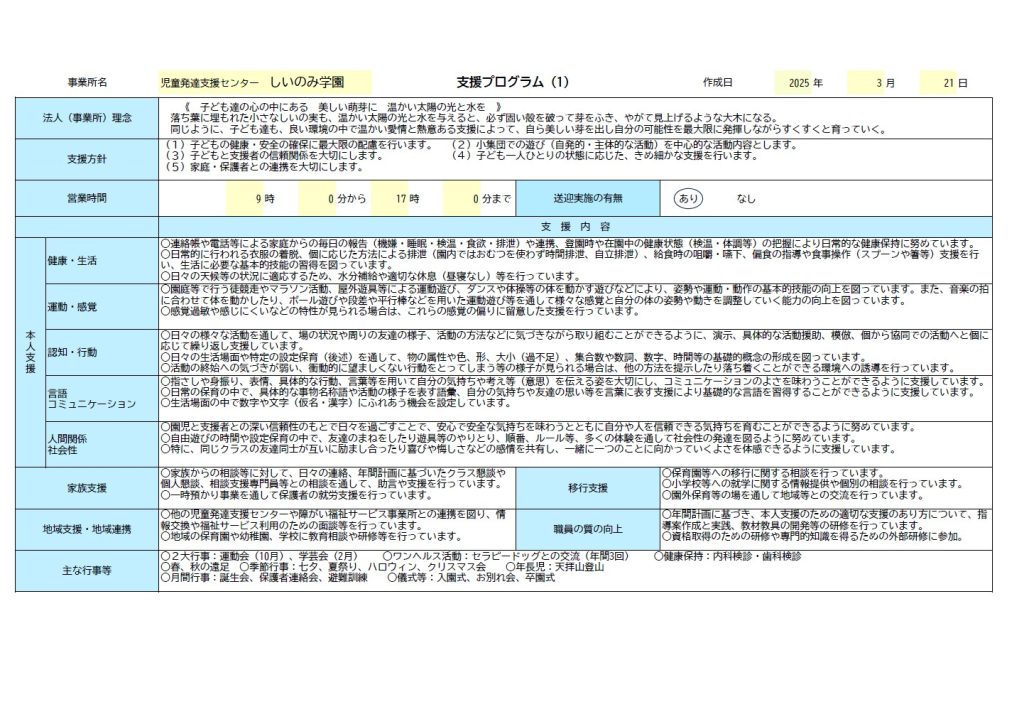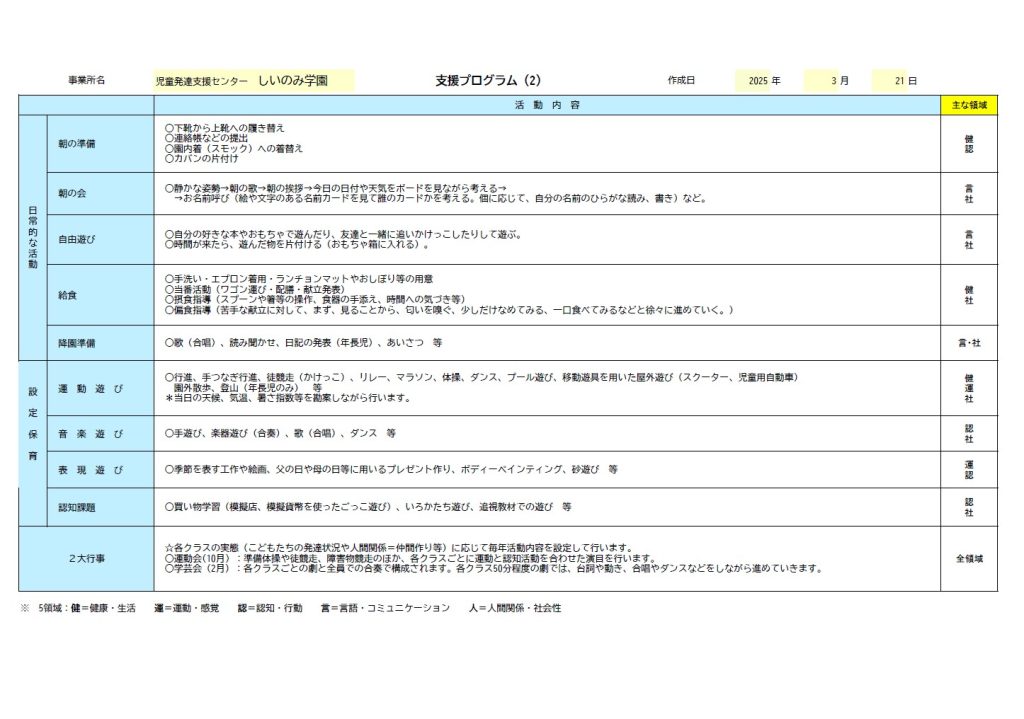しいのみ学園:新着情報
- 2025年04月22日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年04月21日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年04月18日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食 2025/04/18
- 2025年04月08日 しいのみ学園
- しいのみだより 令和7年度4月号
- 2025年03月04日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月28日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月27日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月25日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月20日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月18日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月13日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月04日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年02月03日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月30日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月28日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月23日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月21日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月20日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月16日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月14日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月10日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月09日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2025年01月07日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月24日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月19日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月16日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月13日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月09日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月06日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
- 2024年12月05日 給食だより
- しいのみ学園 今日の給食
認可日
昭和53年4月1日
対象者
福岡市南部地域に住んでいる3~5才の知的障がい・発達障がいのある幼児
クラス編成
| 園児数(定員30名) | 担任数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3才 | 4才 | 5才 | 合計 | ||
| うめぐみ | 9 | 3 | 12 | 5 | |
| ももぐみ | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| さくら | 12 | 12 | 4 | ||
| 合計 | 9 | 10 | 16 | 35 | 13 |
職員構成
- 園長(管理者)
- …1名:髙井 敏雄
- 児童発達支援管理責任者
- …1名
- 児童指導員・保育士
- …13名
- 事務員・用務員
- …3名(2名兼務)
- 栄養士・調理員
- …2名
- 運転士
- …1名
- 嘱託医
- …1名
- 合 計
- …22名
支援方針
- 1健康・安全の確保に最大限の配慮を行います
- ●子どもの健康状態を、毎日・毎時間把握します。
●クラスルームの環境調整や衛生管理に努めます。
●一人ひとりの健康状態に応じて、学習活動・内容を考慮します。
●事件・事故防止のための情報収集・安全対策に努めます。 - 2遊び(自発的・主体的な活動)を、中心的な活動内容とします
- ●子ども同士の集団がもたらす影響力を効果的に活用します。
●遊び(活動)を活発にするため、子どもの興味を生かします。
●子どもが見通しを持ち、自信を持って活動できるよう支援します。 - 3子どもとの信頼関係を大切にします
- ●子どもを褒めて育てることを基本とします。
●子どもと支援者が共に活動し、相互の理解を深めます。
●相互の考えや気持ちを分かり合うため、触れ合う機会を多様に設けます。
- 4一人ひとりの状態に応じた、きめ細かな支援を行います
- ●支援者は、許容的態度の支援を基本とし、必要に応じて即時・最小限の指導を行います。
●働きかけの効果を高め、また、学園生活の安全を確保するため、子どもの行動の予測に努めます。
●子ども一人ひとりの発達の状態に応じて、遊び方や学習内容を柔軟に変化させます。
●注意を集中しやすい環境を整え、発達の適時性に合わせた学習活動を行います。 - 5家庭・保護者との連携を大切にします
- ●学園・クラスからの情報発信を活発に行います。
●子どもの成長・発達についての共通理解を図るため、家庭と学園の情報交換、相談を密に行います。
●保護者参加型の行事を積極的に行います。